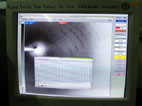■バンガロール最後の日。インド旅も終盤だ。
旅もいよいよ、終わりが近くなってきた。今日、夕刻の便でニューデリーに戻る。
今日は久しぶりにゆっくりと朝寝をした。排気ガスのせいか、疲れのせいか、わたしもA男も急激に喉が痛み始め、かなり咳が出る。米国から持参していた「プロポリス」のスプレーを喉に噴霧するが、効き目なし。
荷物のパッキングをすませたあと、ランチをとるためにブリゲイド・ロードに出る。相変わらずの排気ガスにクラクラしながら、しかし気温が快適なことが救いだな、と思う努力をしながら歩く。
ピザハットに入り、しかしピザは食べず、軽くトマトスープとガーリックトーストをオーダーする。ピザハットのメニューはほとんど「インド式」で、アメリカのメニューとは異なる。
店内は、大音響でBGMが流れている。どの曲がどの曲だか判別しがたい、独特のインド歌謡曲。あまりにも、度を過ぎたうるささなので、店員に音量を下げてくれないかと頼む。
1曲だけは下がったが、次の曲から、またとてつもなく大音量になり、気が変になりそうだ。数名の客が苦情を言っていたが、ほかの客は気にする様子もなく、ここはライブハウスかディスコか、と思う。
腰は痛いし、喉は痛いし、無闇やたらとうるさいし、なんだか気分が冴えない。まあ、そんなこともあるだろう。
■アンジュナのこと。そしてラグバンの大学見学
空港へは午後6時ごろ向かう予定だが、その前にスジャータとラグバンの家に寄ることにしていた。わたしが、バンガロールに着いた日、ラグバンの研究室があるIIS(インド科学技術大学)を見学したいと言っていたのだ。
ホテルのチェックアウトを終え、バンガロール・クラブにロメイシュとウマを迎えにゆき、4人でスジャータたちの家に行く。
ところで2003年は、A男とスジャータの母であるアンジュナが他界してちょうど10年だった。それを記念して、スジャータが母親のメモワールを編集していた。
その本の刷り上がりが、ちょうど今日、印刷所から届いていた。
2色刷のその本は、アンジュナの写真と、「A
MEMORY OF
MUNNA」の文字が記されている。MUNNAとは、アンジュナの愛称だ。
主にはスジャータによるの回想文を中心に、アルヴィンド、ロメイシュを始め、アンジュナを取り巻く人々から寄せられたメッセージが一冊にまとめられている。
随所に写真が掲載され、彼女の人となりを偲ばせる。アンジュナはインドの大学を卒業したあと、英国の大学院で看護学を学んだ。大学院を卒業後はユニセフに勤めていたが、結婚と共に仕事を離れていた。
しかし、自分自身が白血病を病んでいると知ってから、彼女は自分一人が病と闘うのではなく、同様に苦しむ人たちを救い、共に闘おうと、クリニックを開いた。オーガニックの野菜を生産する農場経営も開始し、西洋医学に頼らない、食事療法による、疾病からの救済を目指した。
彼女の貢献は、いくつかの国内誌にも取り上げられ、その記事のコピーもまた、小冊子に転載されていた。
「ポジティブ思考でがんと闘う」
このタイトルではじまる記事には、彼女が米国ボストンのDr.
Ann
Wigmoreのメソッド(方法)を採用した食事療法を行っていることや、彼女が「常に前向きな心で、笑うことが、病を癒す」と信じている、といったことが記されていた。
発病以来、数カ月の余命と医師に告げられていながら、西洋医学による治療を一切拒否して、5年以上も生存している彼女のことを記したその記事中には、いくつもの「奇跡」という文字が見られた。
最近でこそ、西洋医学に頼らずがんを治癒することが、一つの有効な手段として認識されはじめているが、10年以上前のインドでは、かなり画期的なことだったと思われる。
奇しくも今日は、日本の父が、病院での定期検診の結果がわかる日だったので、日本に電話をさせてもらった。
電話での、父の第一声がとても元気だったので、安心した。
しかし実際のところ、数カ月前に抗がん剤で小さくしていたがん細胞に、また動きが出ていたようで、医師からは新年早々にでも入院して抗がん剤治療を初めてはどうかと提案されたようだ。
しかし、衆知の通り、抗がん剤治療は、回を重ねれば重ねるほど、潜在的な免疫力を落としてしまう。骨髄の働きが弱まり、白血球値が落ち、身体の抵抗力が損なわれる。
父の話によると、つい最近、佐賀県にある東洋医学と西洋医学の両方をとりいれた、「ホロトロピック」と呼ばれる医療を採用するクリニックに通い始めたらしく、そこでの治療が父に合っているらしい。
しばらくはそのクリニックに通い、抗がん剤を避けようと思っているとのこと。何が何でも治そうという心意気が、より父の身体を強めているのだと思う。身体の一部としての心が、身体全体に及ぼす影響についてを、改めて考えさせられる。
さて、全部で100冊あるその冊子は、アンジュナと関わりのあった人たちに配られるようで、わたしたちも10冊、米国に持ち帰ることにした。
■スジャータとラグバンの婚姻。アンジュナの死。
ラグバンはIIT(インド工科大学)を卒業したあと、米国のスタンフォード大学の大学院に進み、Ph.D(博士号)を取得、その後イエール大学で教鞭を執っていた。
スジャータはインドの大学を卒業したあと、生物学のPh.Dを取得するため、やはり米国のイエール大学の大学院に進んだ。A男がMIT(マサチューセッツ工科大学)に進学したのと同時期だった。
スジャータとラグバンは、イエール大学で出会った。
そのころ、アンジュナの体調は芳しくなく、休暇のたび、スジャータはインドに帰省し、母との時間を過ごしていた。しかし、いよいよ、アンジュナの未来が、限りあるものと察知したスジャータは、在学中で、まだ若かったにも関わらず、ラグバンとの結婚を決める。
多分、母親に、結婚式を見て欲しかったのだろう。
結婚式を終えたのち、再びスジャータは大学に戻り、怒濤のように多忙な数カ月を送る。博士号取得のためには、それでなくても相当の勉強が必要だというのに、彼女はインドの母を気遣いながら、インドと行き来を繰り返しながら、勉強していた。
次の休暇でインドに戻ったとき、アンジュナは、もう、とても衰弱していた。ロメイシュとスジャータは、A男に帰国するよう連絡をする。
家族みんなに見守られ、アンジュナは、数日後に息をひきとった。
この時期の一連の出来事は、スジャータとA男の心に深い影を落とした。
初めてのアメリカ生活。一人暮らしの不安と寂しさ。競争相手の多い大学。気が遠くなるほど、せねばならぬ勉強。そして最愛の母を案じる気持ち。
アンジュナは、米国の大学に進もうとしているわが子たちの相談に乗り、背中を押し、励ました。たとえ、二人が自分から遠く離れたところに住むことになったとしても、子供たちが羽ばたいていくことは、アンジュナにとっての誇りであり、喜びであった。
2003年の夏、スジャータが我が家に訪れた折、A男に言ったという。最近になって、ようやく、あのころの痛みから、脱皮でき出来たように思う、と。A男にしても、わたしと出会った当初は、よく母親の夢を見て、夜中にうなされ、目を覚ましていた。
"Mother is dying..."
ロメイシュが、A男に帰国を促すため、大学の寮にかけてきた電話。「お母さんが、あぶない」という一言が、鮮明な記憶として、いつまでも心に刻印されていた。
さらには、インドに帰国して、見る影もなくやせ細った母をベッドで見たときの衝撃。一連のシーンが、何度となく夢に現れる。
肉親との別れは、誰にでもあることであり、多分誰もが、長い間、その痛みにさいなまれる。
二人がその痛みから解放されるまでには、長い歳月が必要だった。
■インド科学技術大学の見学
スジャータとラグバンは、スジャータが大学院を卒業し、インドに帰国した直後からバンガロールに住んでいる。ニューデリーよりも気候がよく、のどかなバンガロールが好きで暮らし始めたらしいが、最近の「都会化」には少し閉口しているようだ。
ラグバンはIISで分子生物物理学(molecular
biophysics)の研究をすると同時に、大学で教鞭も執っている。彼は現在、エイズワクチンの研究を中心に行っており、彼の研究成果が認められ、国内外でいくつかの賞を受賞するなど、社会にも貢献している。
彼は一度、MITの研究室に出張していたときにも、わたしたちを内部に案内してくれた。わたしは、言うまでもなく分子生物物理学に精通しているわけがないのだが、研究室ってどんな感じなんだろう、という単純な好奇心から、見学してみたかったのである。
IISの研究室は、古びたビルで、機械も新旧混在で、MITの研究室と比べると少々(かなり)みすぼらしい雰囲気があった。それにしても、研究室、散らかりすぎ。
薄々、気が付いてはいたんだけど、インド人って、全体的に、片づけが下手なんじゃないか。
「こんなことでいいのか?」というくらい、どの研究室も雑然としている。そのくせ「土足禁止」の部屋があったり、「入室前には空気で埃を飛ばす装置」とかが取り付けられてる。意味あるんだろうか、と思う。
しかし、見学の目的は研究室の清潔度チェックではないので、楽しく見学させていただく。
わけわからないなりにも、関心を持っていることを示すため、愚問を連発するわれわれに、ラグバンは、一つ一つの機械の働きなどを説明してくれる。
A男が神妙な顔をして質疑応答を繰り返していたので、あとで「わかってたの?」と尋ねたら、「そんなわけ、ないでしょ」とのこと。そうやろ、そうやろ。
■そして再び、ニューデリーへ
学内の見学を終え、我々は空港へと向かう。スジャータは、マイソールからパタビ・ジョイス師匠がやってくると言うので、ヨガ道場へ行くという。美しいサリーを着て、おめかししている。
ちなみにスジャータは明日、ニューデリーに来るので、ラグバンにしっかりと、別れを告げる。ラグバンと二人で話すことはそんなにないのだが、彼とは短い会話の中にもシンパシーを感じて、とても心を開きやすい。
タクシーの車窓から、バンガロールの町並みを眺めつつ、空港に向かう。この次、この街に来るのはいつだろう。排気ガスよ、改善されていておくれ。そう願いつつ、去る。
さて、恐れていた濃霧による遅れや欠航がなく、飛行機は予定通りに離陸し、深夜、ニューデリーに到着した。ニューデリーはこの1週間で急に冷え込みが激しくなったようで、その寒さに驚く。
空港には、久々にカトちゃん!今日は一張羅のグレーのスーツ(学ラン風)に、やはりグレーのニットキャップを被っている。もう、彼にもすっかりと愛着を感じているわたし……。
そして無事に帰宅。
アメリカのセントラルヒーティングに慣れてしまった身としては、暖房設備の整っていないこの家が、この上なく寒く感じられる。電気ストーブを入れても、温まるのは1メートル四方程度。久しぶりに日本の冬を思い出す。
特にバスルームが寒くてかなわない。シャワーを浴びていても、広すぎる(6畳ほどはある)から全然温まらなくて、ひたすら寒いばかりだ。風呂場は広けりゃいいってもんじゃないと痛感する。
しかも、温水はタンクで加熱されたお湯を使用するため、長時間連続して使えない。
更には、大理石の床や洗面台は氷同然。裸足で歩こうものなら、足が凍て付くし、うっかり裸で鏡の前に向かったりしようものなら、お腹に氷のような洗面台がひゃっと触れて、たまったものじゃない。
第一、大理石は水に濡れると滑りやすいから危険でもある。
一晩で、風邪を引いてしまった。
ちなみに、インドは大理石の産地なので、他国に比べると非常に安価で大理石が手にはいる。何しろ、タージ・マハルは建築物全体が大理石だしね。
欧米のラグジュリアスなホテルなどは「大理石のバスルーム」で高級感を醸し出しているようだが、インドではかなり「日常的な石」なのである。
今朝(2004年1月18日)のニューヨークタイムズの旅行のセクションを読んでいたら、「大理石のお風呂:足許にご注意」という見出しの記事があった。
リッツカールトンやマリオットなど、ラグジュリアスホテルのスイートルームは、高級感を出すために大理石のバスルームを採用しているらしいが、転倒事故が少なくないらしい。
事故への対策などについてがレポートされていた。バスルームでの大理石使用は、検討の余地がありそうだ。